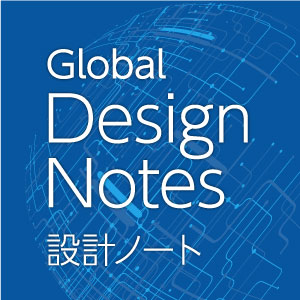アイソレーションアンプ技術ノート(第4回)

1.アイソレーションアンプの概要と特長
アイソレーションアンプの変調/復調部には、アナログ振幅変調回路を採用しています。その理由として、特に高電圧下の環境で使われる事が 多いアイソレーションアンプは、誘導ノイズによる外乱に強く、エラーを起こさない事が要求されるためです。デジタル処理の場合には、 大きな外乱があると、まれに致命的な動作異常、動作停止を起こすことがあります。
一方、アナログ処理方式では、外乱に対してノイズ加算による誤差が多くなりますが、動作異常や停止となるリスクが極めて低いという メリットがあるため、当社はこの方式を採用しています。
主な特長として、以下が挙げられます。
- 独自設計の小型トランスを用いたアナログ入力/アナログ出力
- 高精度の変調/復調回路を内蔵(直線性誤差 ±0.025%FS~)
- 信号入力範囲: ±5V、±10V
- 耐圧(アイソレーション電圧): 1kVACrms ~ 5kVACrms(連続)
- 入力回路のオペアンプは、外部で自由に回路構成する事ができる
- 全ての製品に、絶縁電源回路を内蔵
- 別回路を構成できるよう絶縁された正負電源出力を用意(+Viso、-Viso)
- 小型サイズのモジュール
2.回路構成
アイソレーションアンプの代表的な回路構成を図1(入力絶縁タイプ)及び、図2(出力絶縁タイプ)に示します。
(1) 入力絶縁タイプ

図1 入力絶縁タイプ
(2) 出力絶縁タイプ

図2 出力絶縁タイプ
入力絶縁タイプ(図1)による基本動作
- 変調回路:変調用信号 φ1 による振幅変調
- 復調回路:復調用信号 φ2 による同期整流
- φ1 と φ2 は、同一周期/位相で、デューティ 50% の矩形波
- 発振回路:矩形波発振器、φ2 生成、絶縁電源生成用のトランスを駆動
- 整流回路/平滑回路:変調用信号φ1の出力、絶縁部の内部電源電圧生成、及び外部用絶縁電圧 ±Viso を出力(オペアンプ1個程度の駆動、 オフセット調整等に使用)
- 入力段のオペアンプは、+IN、-IN、FB を外部端子とし、回路を自由に構成可能
3.振幅変調回路/復調回路の基本原理
変調/復調回路の基本原理は、以下(図3)のようになります。

図3
- 信号絶縁トランスの結合容量は、極力小さくして入出力間の交流的な結合/漏れ電流を小さく抑える。
- トランス絶縁回路では R1 が必須
- 変調/復調用の SW 素子には、J-FET 又は CMOS-SW を使用
- 変調/復調用の φ1、φ2 信号はデューティ 50%、同一タイミングの矩形波、但しこの信号間も絶縁する。
Ea:Einをφ1でON/OFFするので、Ein ~ GND(0V)の矩形波となる。
Ea は Ein に完全比例するので振幅変調された矩形波となる。
Eb:トランスにより伝送されたEa
Eo:Eb を SW1 が ON のタイミングで、SW2 にて同期整流し、出力 Eo を得る。
(同期整流とすれば、Ein が負の時、出力も負となる)
・変調
変調波形 Ea は理想的には Ein ~ 0V の矩形波ですが、トランスはインダクタンス素子であり、SW1 の ON/OFF 時にインダクタンスへの
エネルギーの蓄積/放出があるため図4②のようになります。実際の波形は変調回路の方式により異なります。
(φ1、φ2の1周期のフェーズ前半をα、後半をβとします。)

図4
・復調
トランスにより伝送された Eb(=Ea)について、フェーズ前半αを SW2 による同期整流で取出し C で平滑することで、Ein と同等の出力 Eo が得られます。

図5
- 上記の原理は変調周波数の1周期のうちのフェーズ前半αのみを使った半波の変復調方式です。高精度を得る方式としては、1周期のうちの前半と 後半(αとβ)の両方を用いた全波の変復調方式があり、C容量も少なくできるメリットがあります。
※ 当社の高精度製品では、全波の変復調方式を用いています。
4.電源回路
- 当社のアイソレーションアンプは、全て電源を内蔵しています。
- 入力側(入力回路、変調回路)と出力側(復調回路、出力回路)を動作させるために、それぞれ電源供給が必要、入力絶縁タイプの場合は、 入力側に絶縁電源を構成、出力絶縁タイプの場合は、出力側に絶縁電源を構成、3ポートタイプの場合は、入力側出力側共に絶縁電源を 構成しています。
- 電源部は、DC/DC コンバータ構成とし、トランスにより絶縁を確保しますが、入出力間の結合容量を極力小さく抑えたトランスとします。
この結合容量が大きいと交流的に接続された状態となり、絶縁アンプではなくなります。
一般の DC/DC コンバータは、この容量が数 100pF ~ 数1000pF と極めて大きく、交流の漏れ電流が多いので、実用的ではありません。そのため、 それを考慮して設計された電源を内蔵しているアイソレーションアンプを採用した方が、望ましいと考えられます。
次回(第5回)では当社アイソレーションアンプの使用例を紹介致します。
PDF 資料請求
Design_Notes_08:アイソレーションアンプ技術ノート-4
Global Design Notes について
Global Design Notes は、エンジニアのための役立つ技術情報を掲載した WEB 連載です。
- 発行元:グローバル電子株式会社
- 公開メディア:WEB および PDF